近年、話題の「生成AI(Artificial Intelligence:人工知能)」が教育の現場にも入り始めています。文章の作成や問題の解き方の説明など、便利に活用できる一方で、不正利用や誤情報などのリスクも指摘されています。2024年には文部科学省も学校での生成AI利用に関するガイドライン案を発表しました。
この記事では、文部科学省が発表したガイドラインの解説と、家庭でできる対策をわかりやすく解説します。
いま学校で何が起きている?文科省のAI活用方針
文部科学省が発表した「生成AIの学校教育での利用に関するガイドライン案」の生成AIに対する基本的な考え方は以下のとおり。
・人間中心の利活用:生成AIはあくまで教育を支援するツールであり、人間の尊厳や 学びの意義を損なわないよう配慮する必要があります。
・情報活用能力の育成:生成AIの活用を通じて、児童生徒の情報の収集・整理・分析・ 評価・表現といった情報活用能力を強化することが求められます。
・情報モラル教育の充実:生成AIの利活用に伴い、著作権や個人情報の取り扱い、偏見 や差別の再生産といったリスクに対処するため、情報モラル教育の一層の充実が必要 です。
ガイドラインが示す「AIリテラシー教育」の必要性
ガイドラインでは、生成AIを活用する際のリスクとして以下が挙げられています。
・資質・能力の育成に悪影響を与える
・個人情報やプライバシーや著作権侵害の可能性
・外部サービスの利用に起因するリスク
そのため、子どもたちにはAIを正しく判断し活用する力を育むことが求められています。
・AIの情報をうのみにせず、自分で確認する
・個人情報漏洩や著作権侵害となる使用方法について理解を深める
・目的に応じてAIの適切な使い方を判断できる力を育む
家庭でできる子どものAIリテラシー教育
文部科学省のガイドラインでは、生成AIを活用する際の基本的な考え方を示しています。これらの方針に基づき、家庭においても子どもたちが生成AIを適切に活用し、情報を批判的に評価する力を養うことが大切です。
・便利だが全部正しいとは限らず、AIはあくまで「道具」であると伝える
・親子でAIを使用して、情報の正しさを確認すること習慣をつける
・AIだけに頼らず、自分の意見や考えをまとめることも大切と伝える
まとめ:ガイドラインを活かして家庭でもAI教育を
これからの子どもたちは、AIと共に生きる時代を迎えます。怖がって避けるのではなく、正しく理解し、上手に活用する力を育むことが大切です。学校の動きに注目しつつ、家庭でもAIの利用についてオープンに話し合い、ルールや使い方を考えていきましょう。親子で協力して、AI時代の学びを前向きに楽しんでいきたいですね。
参考リンク
- 文部科学省「初等中等教育段階における 生成AIの利活用に関するガイドライン」
https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf
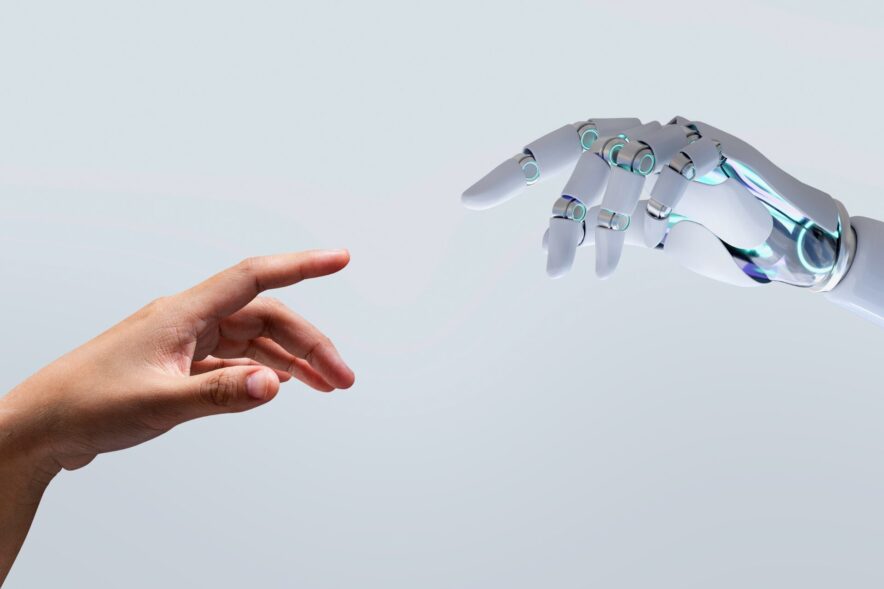
コメント