教育費の準備は「何から始めたらいいかわからない」という声をよく耳にします。しかし、貯め方には王道があります。それが「先取り貯蓄」です。これは、毎月の給料から使う前に一定額を自動的に貯蓄へ回す方法で、教育費だけでなく、住宅資金や老後資金の準備でもよく使われています。
ここでは、先取り貯蓄がなぜ教育費の貯め方として有効なのか、具体的な実践方法や注意点も含めて詳しく解説します。
教育費は“気づけば貯まっている”仕組みが大切
教育資金の特徴は「必要になるタイミングが決まっている」ことです。たとえば、小学校入学時、中学受験、高校・大学進学など、一定の年齢に達したら必ず大きな出費がやってきます。
一方で、これらの出費は急にやってくるわけではなく、10年、15年先に向けて計画的に準備できるものでもあります。だからこそ、「毎月、少しずつ・自動的に・確実に」貯めていく仕組みを作ることが、家計に無理なく備えるポイントです。
先取り貯蓄の仕組みを作る3つの方法
① 銀行口座の自動積立
給与振込口座から毎月決まった日に、別口座(貯蓄専用)へ自動的に一定額を移す方法です。目的別口座(例:○○ちゃん大学進学費)などに分けると、使い込みを防ぎやすくなります。
② 財形貯蓄(勤務先制度)
会社に制度がある場合は「財形貯蓄」も有効です。給与天引きで貯蓄するため、手元にお金が来る前に貯金でき、意志の力に頼らず継続できます。
③ 自動積立型の金融商品(学資保険・投資信託など)
一定額を積み立てながら増やすタイプの金融商品もあります(詳細は2-2で解説)。「貯めながら増やす」ことを意識した商品選びも選択肢のひとつです。
目安は月1〜3万円から
文部科学省や日本FP協会のアドバイスによれば、大学費用だけで300万〜500万円は想定しておくべきとされています。
この金額を18年間で用意するには、たとえば以下のような計算になります。
- 月1万円:18年で216万円
- 月2万円:18年で432万円
- 月3万円:18年で648万円
もちろん途中で受験・塾などの出費があれば取り崩すこともありますが、目標額を持つことで「何となく」から脱却できます。
教育費の準備は“生活費の残り”では難しい
貯蓄に失敗するパターンとして最も多いのが、「余ったら貯める」という考え方です。
これは実質的に“貯まらない仕組み”といっても過言ではありません。
日々の支出に柔軟性があると、ついつい娯楽費や買い物にお金を回してしまい、気づけば「今月も無理だった」が続きます。
先取り貯蓄なら、収入から“強制的に”教育費を差し引くため、
「いつの間にか貯まっていた」という理想的な形を作ることが可能です。
目的別に「仕分け」してモチベーション維持
貯蓄は「見える化」しておくことが大切です。
- 小学校入学費用(ランドセル・制服・教材)
- 中学受験対策費用(塾・模試・受験料)
- 大学進学準備費用(入学金・家賃・引っ越し代)
こうした用途別にシミュレーションしておくと、より現実的な金額が見え、貯蓄への意欲も継続しやすくなります。
学資保険・積立預金・投資信託の比較
教育費の準備といえば、昔から定番とされているのが「学資保険」と「積立預金」。近年では「投資信託」も注目されるようになり、選択肢が広がっています。しかし、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解せずに選ぶと、「思っていたのと違った…」という結果にもなりかねません。
この章では、3つの代表的な教育資金の準備方法を、目的・リスク・流動性などの観点から比較していきます。
比較①:学資保険 〜保障付きの“堅実派”向け〜
特徴:
・保険と貯蓄のハイブリッド型商品
・子どもが一定年齢になったときにまとまったお金が受け取れる
・契約者(親)に万が一のことがあれば、以後の保険料が免除され、満額が支払われる
メリット
- 強制的に積み立てられる(解約しにくい)
- 万一のときの保障機能
- 返戻率が100%を超えることも(長期契約なら)
デメリット
- インフレに弱い(固定利率が多い)
- 中途解約すると元本割れの可能性が高い
- 利回りがほぼゼロ〜年0.5%程度と低い
向いている人
「自分に万が一があったときも、子どもの進学費用を残しておきたい」
「貯金が苦手。確実に積み立てておきたい」
比較②:積立預金(銀行の定期預金)〜リスクゼロだが増えない〜
特徴
・銀行の自動積立定期預金などを使って、毎月コツコツ貯めるシンプルな方法
・満期時に元本+利息を受け取れる
メリット
- 元本保証(1000万円+利息まで預金保護制度あり)
- 出し入れが容易(普通預金と併用しやすい)
- 手続きが簡単で安心感がある
デメリット
- 利息が極端に低い(年0.002%前後)
- インフレに対して資産が目減りする
- 何の対策もなければ「使ってしまう」可能性も
向いている人
「とにかく元本割れはイヤ」
「すぐに使える教育資金を分けて持ちたい」
比較③:投資信託(つみたてNISAなど)〜長期目線で“育てる”〜
特徴:
・株式や債券などに分散投資を行う商品。教育資金に適したインデックスファンドなどが主流
・「つみたてNISA」制度を使えば非課税で運用可能(2024年から制度拡充)
メリット
- 長期運用でインフレに強い
- 年率3〜5%の成長も現実的(元本を超える可能性)
- 少額から始められ、柔軟な金額設定が可能
デメリット
- 元本保証なし(価格変動リスクあり)
- タイミングによっては元本割れのまま出金の恐れ
- 投資知識・継続管理が多少必要
向いている人
「10年以上の長期スパンで教育資金を増やしたい」
「物価上昇・低金利に対応した資産形成をしたい」
比較表:3つの特徴をまとめると
| 項目 | 学資保険 | 積立預金 | 投資信託(NISA等) |
|---|---|---|---|
| 元本保証 | △(条件付き) | ◎ | × |
| 利回り | 低(0.5%未満) | 極めて低い | 中〜高(3〜5%) |
| 流動性 | 低い | 高い | 中程度 |
| インフレ耐性 | 弱い | 弱い | 強い |
| 向いてる人 | 確実に貯めたい | 安全重視 | 長期で増やしたい |
どれを選ぶかは「性格×期間×目的」で判断
どれか一つに絞るのではなく、たとえば…
- 幼児期〜小学生:学資保険で堅実に積立
- 中学以降〜大学:NISAで長期運用
- 生活予備費:積立預金でいつでも使える資金確保
以上のように、資金確保は「組み合わせて使う」のが現代のスタンダードです。
教育資金準備におすすめのタイムライン
教育資金の準備は「思い立ったが吉日」です。とはいえ、子どもが生まれてから大学を卒業するまでの間に、どの時期にどのくらい準備を進めていくべきなのか、目安がないと不安ですよね。
ここでは、教育資金の準備において“いつ・どのくらい・どうやって”お金を備えていくか、ライフステージ別に理想的なタイムラインをご紹介します。
ステージ①:0〜5歳(幼児期)=積立開始の「黄金期」
- 推奨アクション:
- 先取り貯蓄を開始(月1〜2万円が目安)
- 学資保険を契約するならこの時期に
- つみたてNISAの導入も視野に入れる
子どもが生まれてすぐは教育費に対する実感がないものの、この時期が最も貯めやすいゴールデンタイムです。幼稚園までは支出が比較的少なく、貯蓄に回せる余裕がある家庭が多いのが特徴です。
この段階で教育費の“土台”をしっかり作っておけば、中学・高校でかかる塾代や習い事代にも柔軟に対応できます。
ステージ②:6〜11歳(小学校)=家計のバランスを再確認
- 推奨アクション:
- 教育費の見直し(習い事・教材費など)
- 中学受験の予定があれば、その費用を逆算して積立
- 投資信託など、時間を味方にする運用継続
小学生になると、習い事や塾通いが始まり、教育関連の出費が徐々に増加します。特に中学受験を考えている場合は、4〜6年生で年間50〜100万円程度の塾代が発生することも。
支出が増える反面、まだ大学資金には10年以上の猶予があります。焦らず「中期の貯蓄・長期の運用」を組み合わせながら、負担を分散させる時期です。
ステージ③:12〜15歳(中学校)=教育費が急上昇する“山場”
- 推奨アクション:
- 受験に備えて塾・模試代を優先確保
- 高校進学時の入学金・制服費用を事前準備
- 学資保険の満期が近づくため、使い方の計画を
この時期は、塾や模試代が最も高くなるステージです。家計にとっての「教育費ピーク」のひとつであり、計画なしでは思わぬ赤字に転落するリスクも。
この時期までに「最低でも100万円以上の貯蓄があること」が、家計の安定に大きく寄与します。逆にこの時点での資金不足は、奨学金やローンに頼らざるを得ない未来につながりかねません。
ステージ④:16〜18歳(高校)=進学の現実と向き合う時期
- 推奨アクション:
- 大学進学費用(100万円以上)を確実に準備
- 自宅通学か下宿かでシミュレーション
- 奨学金や給付型支援制度を調査・申請
高校時代は「受験」「合格」「入学準備」という一連の流れがあり、精神的・経済的に最も慌ただしい時期です。進学先が確定すると、入学金+前期授業料で100万円以上の即金が必要になるケースも多いため、ここでの準備不足は命取りです。
また、住居の確保(下宿やアパート契約)にもまとまった資金が必要となるため、高2の段階で進学費用の目標額が貯まっているのが理想です。
ステージ⑤:18歳以降(大学生)=備えから“支出”へ
- 推奨アクション:
- 準備してきた資金を計画的に取り崩す
- 支出管理を徹底し、無駄を省く
- アルバイト・奨学金とのバランスを考慮
大学生になった後は、これまで積み上げてきた資金を**「いかに計画的に使っていくか」がカギ**になります。毎年の学費・生活費に合わせて取り崩し方を設計することで、4年間の資金切れを防ぎます。
最終的に必要な教育費準備のモデル例
| 期間 | 毎月の貯蓄額 | 合計(18年間) |
|---|---|---|
| 月2万円 | 432万円 | 国公立大学+通学向け |
| 月3万円 | 648万円 | 私立文系大学向け |
| 月4万円 | 864万円 | 私立理系・下宿向け |
このように、教育資金の準備には「タイミングと戦略」が不可欠です。
続きは下の記事をご覧ください。
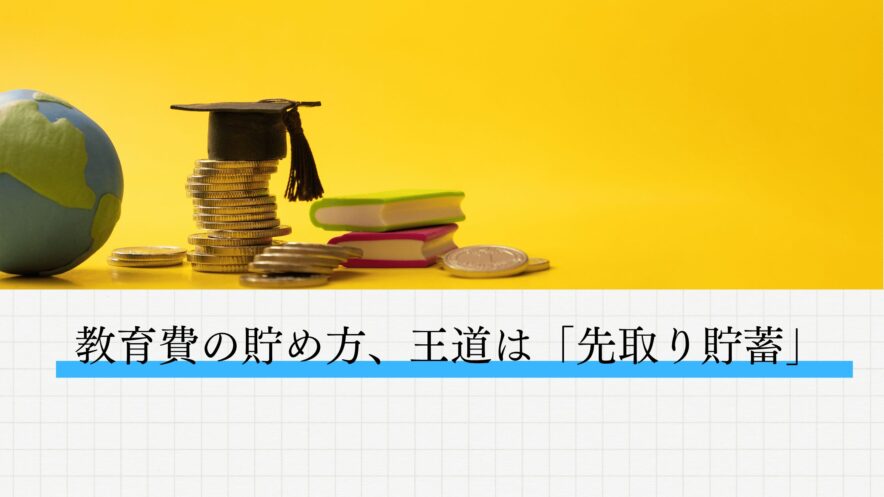
コメント